大病院向け電子カルテ市場は、医療のDX加速や運用効率化ニーズの高まりを背景に激しい競争を繰り広げています。
さらに、システム選定で重視すべき観点(拡張性、連携性、UI/UX、価格設計、サポート体制)も整理し、「大病院が本当に選ぶべき電子カルテ」像を提示します。
導入検討中の医療機関経営者・情報部門担当者必読の比較ガイドです。
大病院向け電子カルテのシェアTOP3
大病院向け電子カルテ市場は、多診療科連携や地域医療連携、膨大なデータ管理など高度な機能が求められる分野です。
日経メディカルの調査によると、シェア上位は「Medicom‐HRシリーズ(ウィーメックス)」「Dynamics(ダイナミクス)」「M3 Digikar(エムスリーデジカル)」の3製品で、いずれも高い信頼性と機能性を備えています。(出典:日経メディカル「第22回 【医師976人に聞いた】電子カルテ導入シェアランキング2023速報 」)
Medicom‐HRシリーズ(ウィーメックス株式会社(PCHグループ))21.1%

ウィーメックス株式会社(PCHグループ)が提供する「Medicom‐HRシリーズ」は、長年にわたり医療現場で培った信頼性と豊富な導入実績を持つ電子カルテです。特に大病院で必要とされる複数診療科の連携や、外来・入院・検査・薬剤部門までを統合的に管理できる点が高く評価されています。
また、診療ガイドラインやレセプト業務への対応力も充実しており、現場の事務作業を軽減しつつ診療効率を高めます。さらに、全国規模での導入実績に基づく安定したサポート体制も魅力で、シェア21.1%という数字が示す通り、多くの大病院から選ばれる定番的存在です。
Dynamics(株式会社ダイナミクス)14.9%

株式会社ダイナミクスが展開する「Dynamics」は、シェア14.9%を獲得する大病院向け電子カルテです。特長は、ユーザー目線で設計された操作性と柔軟なカスタマイズ機能にあり、各病院の診療科や運用フローに合わせて最適化できます。診療情報や検査データを一元的に管理できるほか、他システムとの連携性も高く、地域医療連携や紹介患者対応などにもスムーズに対応可能です。
さらに、導入から稼働までのスピードや、専任スタッフによるサポート体制も評価されており、変化の激しい医療現場にフィットする実用性の高さが魅力です。効率性と拡張性を重視する病院に選ばれる理由がここにあります。
M3 Digikar(エムスリーデジカル株式会社)14.3%

エムスリーデジカル株式会社が提供する「M3 Digikar」は、シェア14.3%を誇る大病院向け電子カルテで、データ活用やクラウド型運用を重視する医療機関に適しています。大規模病院においては、診療データの集約と分析を通じて経営改善や診療の質向上を図れる点が大きな魅力です。
また、M3グループのネットワークを活かし、最新の医療情報や診療支援サービスとの連携もスムーズ。クラウド基盤を活用することで、システムの保守性や拡張性も高く、将来的な医療DXへの適応力も期待できます。サポート面でも利用者の声を反映した改善が進められており、データドリブンな経営や効率的な診療体制を目指す大病院に最適な選択肢といえます。
電子カルテの普及率は?
電子カルテの普及率は年々上昇しており、大病院ではほぼ浸透していますが、中小病院やクリニックではまだ導入が進みきっていない状況です。(出典:厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」)
大病院での普及率
400床以上の大病院における電子カルテの普及率は、平成20年時点では38.8%に留まっていました。しかし、その後の約10年間で急速に導入が進み、令和2年には91.2%という高水準に到達しています。
これは、大病院特有の診療科の多さや膨大な患者データ管理の効率化が強く求められた結果といえます。また、診療報酬制度や医療DXの推進政策も後押しとなり、電子カルテは大病院にとって欠かせないインフラとなりました。現在では、ほぼ全ての大病院が電子カルテを活用し、医療の質や業務効率化を支える重要な役割を果たしています。
中小病院での普及率
400床未満の中小病院では、平成20年時点での普及率は平均15.8%と低水準に留まっていました。令和2年時点では61.8%まで上昇しており、大幅な伸びを見せていますが、大病院に比べると依然として導入率には差があります。
中小病院では、導入費用や運用コスト、人材リソースの不足がハードルとなり、普及が遅れてきた背景があります。それでもクラウド型の電子カルテの登場や、補助金制度の活用によって導入が進んでおり、地域医療における情報共有や効率化に寄与し始めています。今後はさらに導入が加速すると見込まれます。
クリニックでの普及率
クリニックの電子カルテ普及率は、平成20年には14.7%と低い数値でしたが、令和2年には49.9%まで上昇しています。半数近くのクリニックで導入が進んでいるものの、依然として約半数は紙カルテを利用している状況です。
クリニックにおいては、導入コストの負担や、既存業務との相性、スタッフ教育にかかる時間などが普及を妨げる要因となっています。
しかし近年では、クラウド型電子カルテや低コストプランの普及により、導入のハードルは下がりつつあります。患者サービス向上や診療効率化の観点からも、今後さらなる普及拡大が期待されます。
おすすめの電子カルテ10選|特徴や料金を比較!
電子カルテは機能や料金体系が多様で、クリニックから大病院まで導入ニーズもさまざまです。ここではおすすめの10選を特徴とともに紹介します。
エムスリーデジカル

エムスリーデジカルが提供する「M3 Digikar」は、クラウド型の電子カルテとして柔軟な運用が可能です。診療データの集約・分析を得意とし、経営改善や診療の質向上を図りたい医療機関に適しています。
M3グループの強みを活かし、医師向け情報サービスやオンライン診療との連携もスムーズに実現。クラウド型のため初期導入コストを抑えられる点も魅力で、中小病院やクリニックに人気があります。また、導入後も利用者の声を反映して改良が行われ、現場に即した進化が続いています。
ドクターソフト

「ドクターソフト」は、シンプルで直感的な操作性を重視した電子カルテです。小規模クリニックや新規開業医向けに設計されており、操作習熟に時間がかからない点が評価されています。レセプトコンピュータ機能も一体化しているため、請求業務まで一括管理でき、業務効率を大幅に改善します。
料金も比較的リーズナブルに設定されており、コストを抑えて導入したい医療機関に最適です。必要最低限の機能から始めて段階的に拡張できるため、開業後の成長にも柔軟に対応できる点も大きな特徴です。
メディカル革命(Medicom-HRfクラウド版)

「Medicom-HRfクラウド版」は、ウィーメックスが提供するクラウド型の電子カルテです。大病院でも評価の高いMedicomシリーズをベースに、中小規模医療機関でも利用しやすい形に最適化されています。クラウド基盤を活用することで、システム保守やサーバー管理の負担を軽減し、常に最新機能を利用可能。
セキュリティ対策も強固で、医療情報を安全に管理できます。さらに、診療所規模に合わせた料金プランが用意されており、スモールスタートから安定運用まで幅広い選択肢を提供しています。
ユビークリニック(Ubie)

「ユビークリニック」は、AIを活用した問診システムを強みとする電子カルテです。患者の来院前に症状や情報を入力してもらうことで、診察の効率化と医師の負担軽減を実現します。電子カルテとの連携により、診療記録が自動生成される仕組みも搭載しており、事務作業の時間短縮に寄与します。
クラウド型のため導入が容易で、スマートフォンやタブレットを通じた利用も可能です。料金体系も明確で、初期費用を抑えて利用を始められる点から、クリニックを中心に急速に普及しています。
きりんカルテ

「きりんカルテ」は、地域密着型クリニックでの導入が進んでいる電子カルテです。直感的なUIに加えて、予約管理や会計機能も統合されており、小規模医療機関の運営を強力にサポートします。
クラウドベースで提供されるため、インターネット環境があればどこからでも利用可能。サポート体制も充実しており、導入後の不安を解消してくれます。料金設定は中小規模向けに最適化されており、費用対効果を重視するクリニックに人気です。電子カルテ初心者にも扱いやすい設計が魅力です。
BrainBoxCloud
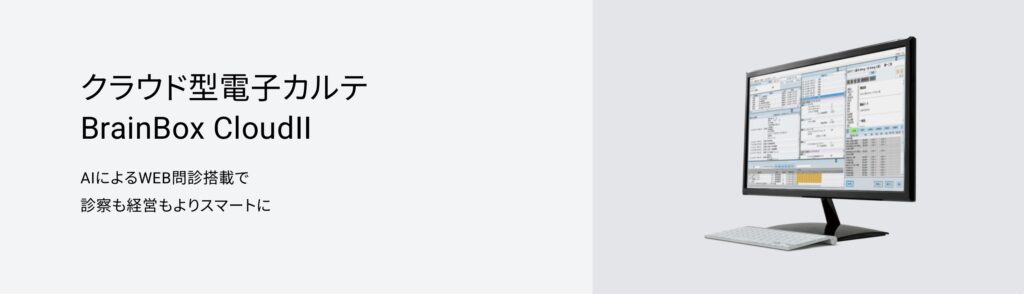
「BrainBoxCloud」は、高度な画像管理や診療支援に強みを持つ電子カルテです。放射線科や整形外科など、画像診断を多用する診療科で特に評価されています。クラウド基盤で提供されるため、サーバーの設置や管理が不要で、スムーズに導入できるのもポイントです。
また、システムの拡張性が高く、将来的な機能追加にも対応可能。診療データや検査画像を一元管理できることで、医療現場の効率化と情報共有を実現し、チーム医療の推進に役立ちます。
Qualis Cloud

「Qualis Cloud」は、操作性とコストパフォーマンスのバランスに優れたクラウド型電子カルテです。導入コストを抑えながらも、診療業務に必要な機能を幅広くカバーしている点が特徴です。レセプト請求や予約管理機能も備えており、クリニック経営をトータルで支援します。
クラウド型であるため、診療データのバックアップやセキュリティ管理が常に最新状態に保たれ、安心して利用できます。中小規模のクリニックに最適なソリューションとして導入が進んでいます。
MRN

「MRN」は、柔軟なカスタマイズ性を持ち、幅広い診療科で利用されている電子カルテです。特に専門性の高い診療科でも対応できるよう設計されており、医師ごとの診療スタイルに合わせた運用が可能です。大規模病院からクリニックまで幅広い導入実績があり、サポート体制の充実度も高評価。
さらに、データ連携機能を備えており、地域医療連携や紹介患者対応もスムーズに行えます。長期的に安定して利用できる電子カルテを探している医療機関に適した選択肢です。
CLIUS

「CLIUS」は、スタートアップ企業が開発したクラウド型電子カルテで、デザイン性と使いやすさに特化しています。直感的な操作性により、スタッフ全員が短期間で慣れることができ、業務効率の改善に寄与します。
さらに、オンライン診療や電子処方箋とのスムーズな連携機能を持ち、最新の医療DXニーズに対応。導入コストも抑えられており、特に新規開業クリニックに人気があります。利用者からのフィードバックを積極的に取り入れた改善も特徴です。
Medicom-HRfオンプレミス版
「Medicom-HRfオンプレミス版」は、ウィーメックスが提供する大病院向けの電子カルテです。サーバーを院内に設置するオンプレミス型のため、データの保有・管理を自院で完結できる点が大きな特徴です。
セキュリティ面の安心感が高く、独自の運用ルールや高度なカスタマイズが可能であるため、大規模病院や大学病院を中心に選ばれています。導入コストや運用負担はクラウド型に比べて大きいものの、安定性と拡張性を重視する施設にとっては信頼できる選択肢です。
電子カルテを選ぶ際のポイントは?
電子カルテを選ぶ際には、システム形態や費用、必要な機能、サポート体制などを総合的に比較検討することが重要です。
クラウド型かオンプレミス型かのシステム形態
電子カルテには、クラウド型とオンプレミス型の2種類の提供形態があります。クラウド型はインターネット環境があれば利用可能で、サーバー管理やシステム更新の手間が不要なため、小規模クリニックや低コストで導入したい施設に向いています。
一方、オンプレミス型は院内にサーバーを設置する方式で、セキュリティ面やカスタマイズ性に優れており、大規模病院や独自の運用ルールを持つ医療機関に適しています。導入の柔軟性やコスト、運用体制を考慮して、自院に最適な形態を選ぶことが大切です。
初期費用・月額費用が予算に合っているか
電子カルテの導入にあたっては、初期費用とランニングコストの両方を見極める必要があります。クラウド型は初期費用が比較的低く抑えられ、月額料金で運用できるのが特徴です。
一方、オンプレミス型はサーバー設置やシステム構築にまとまった初期費用が必要ですが、長期的に使う場合はトータルコストを抑えられるケースもあります。また、補助金制度の活用によって費用負担を軽減できる場合もあるため、予算と支払い形態を見比べた上で選定することが重要です。
レセコン一体型か分離型か
電子カルテとレセプトコンピュータ(レセコン)の関係も重要なポイントです。レセコン一体型は、診療記録からレセプト作成までをシームレスに行えるため、事務作業を効率化できます。
特に小規模クリニックでは一体型を選ぶことで業務フローがシンプルになります。一方、分離型は電子カルテとレセコンが独立しているため、柔軟に組み合わせを選べるのが利点です。すでにレセコンを導入済みの医療機関や、特定機能に特化したシステムを求める場合には分離型が適しており、自院の状況に合わせた選択が求められます。
在庫管理・予約管理・画像連携など必要機能の有無
電子カルテを選ぶ際は、診療科や運営スタイルに合わせた機能の有無を確認することが欠かせません。例えば、小児科や内科では予約管理や予防接種スケジュール管理が重要であり、整形外科や眼科では画像診断とのスムーズな連携が必須です。
また、院内薬局を持つクリニックや病院では、薬剤の在庫管理機能があると効率的です。必要な機能が最初から備わっているのか、あるいは追加で拡張できるのかを見極めることで、無駄なコストをかけずに最適なシステムを導入できます。
サポート体制や操作性の分かりやすさ
電子カルテの導入後には、スタッフ全員が日常的に利用することになるため、操作性とサポート体制も大きな判断基準となります。直感的に操作できるUIを備えていれば、習熟にかかる時間が短縮され、診療の妨げになりません。
また、トラブル発生時に迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかどうかも重要です。電話やオンラインでのサポート、定期的なアップデート対応など、ベンダーの支援内容を比較することで、安心して長期的に利用できる環境を構築できます。
電子カルテを導入する流れは?
電子カルテ導入は段階を踏んで進めることで失敗を防げます。目的の明確化から運用開始までの基本的な流れを整理しましょう。
①導入目的を明確化し、要件を整理する
電子カルテを導入する際には、まず「なぜ導入するのか」を明確にすることが重要です。業務効率化や診療の質向上、情報共有の強化など目的を整理することで、必要となる機能やシステムの方向性が定まります。
その上で、診療科や規模に応じた要件をリスト化しておくと、メーカー選定の際にブレが生じにくくなります。また、スタッフの意見を反映させることで、現場での使いやすさや業務効率にも直結します。最初の段階で導入の目的と要件をしっかり固めることが、成功の第一歩です。
②複数メーカーから情報収集・相見積もりを取る
導入要件が整理できたら、次に複数メーカーから情報を集め、比較検討を行います。電子カルテにはクラウド型やオンプレミス型、レセコン一体型などさまざまなタイプがあり、それぞれの特徴を把握することが大切です。価格や機能、サポート内容を比較するために相見積もりを取ることは必須です。
複数社の提案を比較することで、自院の予算や運営スタイルに合った最適なシステムを見極められます。特に費用面では、初期費用とランニングコストの両方を把握しておくことが重要です。
③デモや体験版を利用して操作性を確認する
電子カルテは日々の診療に直結するシステムであるため、実際に操作性を確認することが不可欠です。メーカーによってはデモや体験版を提供しており、導入前に実際の画面や操作フローを試せます。これにより、スタッフが直感的に使えるか、業務の流れに支障がないかを確認できます。
導入後に「使いにくい」と感じてしまうと、業務効率が下がるだけでなく、スタッフの不満も増えかねません。そのため、事前に複数のシステムを体験し、比較することが失敗を防ぐ大きなポイントとなります。
④契約後にハードやネットワーク環境を整備する
契約が決まったら、運用開始に向けて必要なハードやネットワーク環境を整備します。クラウド型であれば高速で安定したインターネット環境が必須となり、オンプレミス型であればサーバーや専用端末を院内に設置する必要があります。
さらに、セキュリティ対策としてファイアウォールやバックアップ体制の構築も重要です。導入前にインフラをしっかり整えておくことで、稼働後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用が実現します。準備段階でのチェックリスト作成も有効です。
⑤スタッフ研修を実施し、運用を開始する
最後に、スタッフ研修を行い、実際の運用をスタートします。電子カルテは院内の全スタッフが利用するため、全員が一定レベルで操作できるように教育を行うことが欠かせません。メーカーが研修プログラムを提供している場合も多く、それを活用することで効率的に習熟が進みます。
初期段階ではサポート担当者に立ち会ってもらい、トラブルや疑問にすぐ対応できる体制を整えると安心です。導入後も定期的に活用状況を見直し、改善点をフィードバックすることで、電子カルテを最大限に活用できます。
電子カルテを導入するメリット
電子カルテの導入は、業務効率化だけでなく診療の質や患者サービス向上にもつながります。主なメリットを具体的に解説します。
診療記録の検索・共有が容易になる
電子カルテでは、患者ごとの診療記録を瞬時に検索でき、必要な情報にすぐアクセスできます。紙カルテのようにファイルを探す手間がなく、過去の診療歴や検査結果もスムーズに確認可能です。また、院内の複数診療科やスタッフ間で同時に情報を共有できるため、チーム医療の質が向上します。
地域医療連携や紹介状のやり取りも効率化され、情報伝達のタイムロスを削減。結果として、診療のスピードアップや患者への的確な対応が可能になり、医療現場全体の円滑な運営に寄与します。
売上や診療データを自動集計できる
電子カルテは、診療記録や会計データを自動で集計・分析できる機能を備えています。これにより、日々の売上や診療件数、保険請求データを簡単に確認でき、経営状況の可視化が可能となります。紙ベースでは時間のかかる集計作業も自動化されるため、スタッフの業務負担を軽減できます。
また、データ分析を活用することで、診療科ごとの収益性や患者数の推移を把握でき、経営改善やサービス向上に直結。医療機関の経営判断を迅速かつ正確に行える点は大きなメリットです。
在庫や検査結果と連携して効率化できる
電子カルテは、検査機器や薬剤在庫システムと連携することで業務を効率化します。検査結果が自動でカルテに反映されるため、手入力の手間や記録ミスを防止でき、診療の正確性が向上します。また、薬剤や医療材料の在庫管理と結びつけることで、使用状況や発注状況をリアルタイムで把握可能です。
これにより、欠品や過剰在庫を防ぎ、コスト削減にもつながります。診療データと周辺業務がシームレスに統合されることで、院内全体のワークフローを改善できるのが特徴です。
ペーパーレス化で保管スペースを削減できる
紙カルテを使用している場合、膨大なファイルを保管するスペースが必要となりますが、電子カルテを導入することでペーパーレス化が進み、物理的な保管場所を大幅に削減できます。
これにより、院内スペースを有効活用できるだけでなく、ファイルの紛失リスクや劣化の心配も解消されます。
さらに、電子データはバックアップやセキュリティ対策を行うことで、長期保存や災害対策にも強い体制を整えられます。物理的・管理的コストの削減につながる点は大きな魅力です。
患者サービスや診療の質を向上できる
電子カルテの活用は、患者サービスの向上や診療の質の改善にも直結します。診療記録や検査結果を迅速に参照できるため、診察時間を効率化し、患者への説明もわかりやすく行えます。また、過去データを活用した治療計画や予防医療への応用も可能で、より精度の高い診療が実現します。
さらに、患者ポータルやオンライン診療と連携できるシステムでは、予約や結果確認を患者自身が行えるため利便性が高まります。結果として、患者満足度の向上と医療機関の信頼性強化につながります。
電子カルテを導入するデメリット
電子カルテは多くのメリットがある一方で、導入や運用に伴うコストやリスクも存在します。代表的なデメリットを解説します。
初期費用や月額費用などコストが発生する
電子カルテの導入では、サーバーや端末の購入費用、ソフトウェアのライセンス料など初期投資が必要です。クラウド型の場合は初期費用を抑えられる反面、月額利用料が発生し、長期的に見ると一定のコスト負担が続きます。
また、オプション機能やサポート契約を追加するとさらに費用が膨らむこともあります。補助金を活用できるケースもありますが、予算に応じたシステム選びを怠ると経営を圧迫する可能性もあるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
システム障害や通信トラブル時に診療が滞る
電子カルテはシステムに依存するため、障害や通信トラブルが発生すると診療業務に支障をきたします。クラウド型の場合はインターネット環境が不安定になるとカルテにアクセスできず、オンプレミス型でもサーバー障害が起これば診療が停止してしまう可能性があります。
これに備えて、バックアップ体制や紙カルテによる緊急対応手順を用意しておくことが重要です。万が一のトラブルに対して迅速に復旧できるサポート体制があるかどうかも、導入前に確認すべきポイントです。
スタッフへの操作教育やルール整備が必要
電子カルテはスタッフ全員が日常的に利用するため、導入時には操作研修や運用ルールの整備が欠かせません。直感的なUIを備えたシステムでも、初めて扱うスタッフにとっては一定の学習が必要です。
また、入力方法やアクセス権限のルールを定めておかないと、情報の不備や運用トラブルにつながります。導入当初は業務に慣れるまで一時的に診療効率が下がる可能性もあるため、研修計画やマニュアル整備を事前にしっかり行うことが求められます。
iOSやソフト更新に影響を受けるリスクがある
特にタブレット型やクラウド型の電子カルテは、iOSやソフトウェアのアップデートによる影響を受ける場合があります。OSの更新によって一部機能が利用できなくなったり、不具合が発生したりするリスクがあるため注意が必要です。
メーカー側で迅速にアップデート対応が行われることもありますが、更新のタイミングによっては一時的に業務に支障をきたすこともあります。導入前にサポート体制や更新ポリシーを確認し、安定的に運用できる環境を整えることが重要です。
個人情報漏洩などセキュリティリスクがある
電子カルテには患者の個人情報や診療データが集約されるため、セキュリティ対策が不十分だと情報漏洩のリスクが高まります。外部からの不正アクセスや内部の不注意による情報流出など、さまざまな脅威が想定されます。
特にクラウド型の場合は、インターネットを介してデータを扱うため、暗号化や多要素認証といった高度なセキュリティ対策が必須です。導入時にはベンダーのセキュリティ体制を確認し、院内でもアクセス権限管理やスタッフ教育を徹底することが求められます。
電子カルテを探すなら無料のコンシェルジュへ!
これから電子カルテの導入をお考えの方は、無料の一括資料請求サービスをご利用ください。
電子カルテコンシェルジュでは、複数会社への一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。
非公開情報も無料で提供させていただきます。まずはお気軽にご相談ください

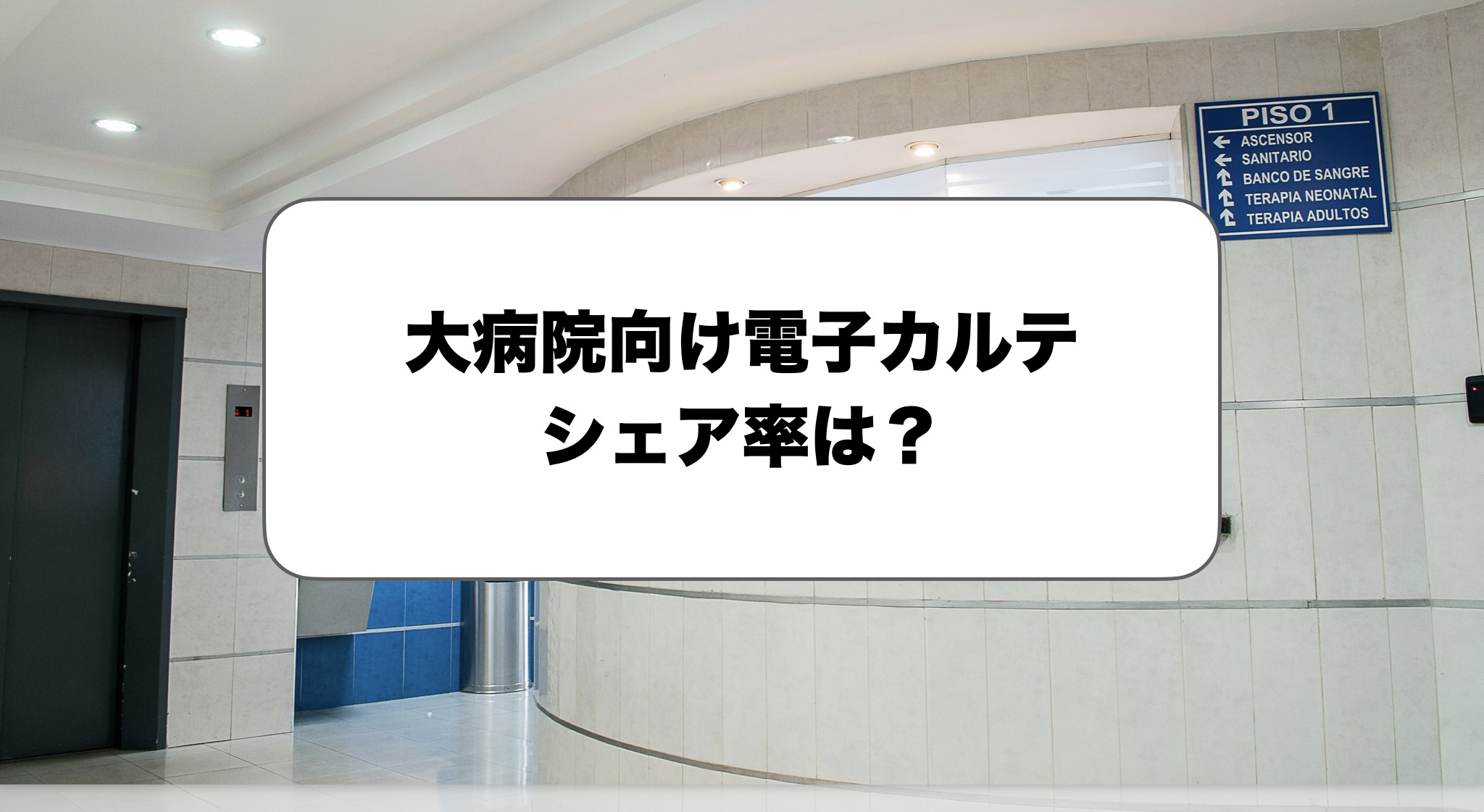
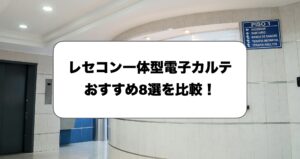
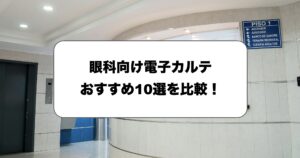
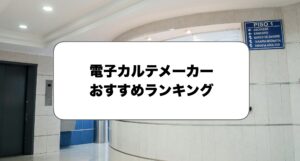
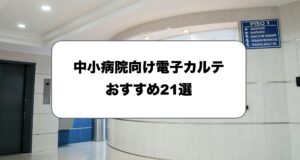
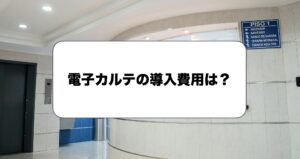
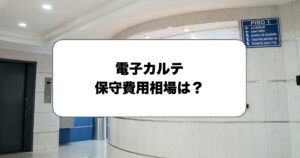
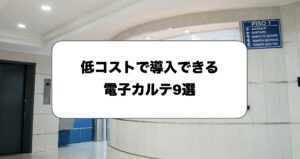
コメント