電子カルテの導入費用は、医療機関の規模や選ぶシステムの種類によって大きく変動します。
初期費用に加え、月額利用料や保守費用など継続的なコストも発生するため、事前に相場を把握しておくことが重要です。
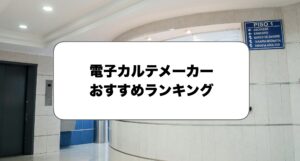
電子カルテの基礎知識について
ここでは、電子カルテの概要や種類について解説します。
電子カルテとは?
電子カルテとは、患者の診療記録や検査結果、投薬履歴などを電子的に一元管理するシステムです。従来の紙カルテでは検索や共有に時間がかかり、記録の保管や紛失リスクも課題となっていました。これに対し、電子カルテは入力した情報を即座に閲覧・共有できるため、医師・看護師・事務スタッフが連携しやすくなります。
また、診療データを蓄積することで診療報酬請求や統計分析もスムーズに行え、経営面でもメリットがあります。さらに、災害時や患者の転院時にも情報を迅速に引き継げる点が注目されており、医療の質と安全性を高める必須のツールとなっています。
電子カルテの種類について
電子カルテには大きく分けてクラウド型とオンプレミス型があり、導入コストや運用方法に違いがあります。電子カルテは導入形態によって「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類に大別されます。
以下で、それぞれの特徴をさらに詳しく解説します。
クラウド型
クラウド型電子カルテは、ベンダーが提供するクラウドサーバーにアクセスして利用する形態です。ソフトウェアやサーバーを自院に設置する必要がなく、初期費用を大幅に削減できる点が特徴です。料金は月額制や年額制が一般的で、導入後すぐに利用を開始できる利便性があります。
また、自動でアップデートやセキュリティ対策が施されるため、専門知識がなくても最新環境を維持できます。ただし、インターネット環境が不安定だと業務に支障をきたす可能性があり、停電や通信障害への備えが必要です。小規模クリニックやコストを重視する医療機関に向いている導入形態といえるでしょう。
オンプレミス型
オンプレミス型電子カルテは、医療機関の施設内にサーバーを設置し、自院でシステムを運用する形態です。クラウド型に比べ初期費用は高額ですが、セキュリティ面で安心できるほか、独自の要望に合わせて柔軟にカスタマイズできる点がメリットです。大規模病院など、患者数が多く高機能を求める医療機関に適しています。
インターネット接続が不要で院内ネットワークのみで運用可能なため、通信障害の影響を受けにくいのも特徴です。一方で、システムの保守やアップデートは自院で行う必要があり、専門知識を持つ人材やベンダーとの継続的な契約が欠かせません。長期的には安定運用と信頼性を確保できる導入方式として評価されています。
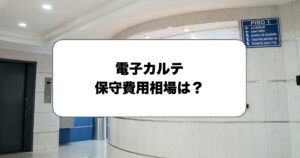
電子カルテ導入費用は?
電子カルテの導入費用はシステムの種類や規模によって大きく異なります。クラウド型は比較的安価に始められる一方、オンプレミス型は高額ですが機能性に優れます。
さらに月額料金の目安も把握することで、総コストをイメージしやすくなります。
クラウド型電子カルテの導入費用(100〜200万円)
クラウド型電子カルテの導入費用はおおよそ100〜200万円程度とされ、オンプレミス型に比べて初期投資が抑えられるのが特徴です。サーバーを自院に設置する必要がないため、導入時の工事費や専用設備費用も不要です。
また、ソフトウェアの更新やセキュリティ対策はベンダー側が行うため、運用負担が軽減されます。小規模クリニックや開業医にとって導入しやすく、スモールスタートが可能な選択肢といえるでしょう。ただし、安定したインターネット環境が不可欠であり、通信障害時のリスクは事前に考慮しておく必要があります。
オンプレミス型電子カルテの導入費用(250〜400万円)
オンプレミス型電子カルテの導入費用はおおよそ250〜400万円と高額で、クラウド型に比べて大きな初期投資が必要です。自院内にサーバーや専用機器を設置するため、工事費や機材費が発生します。その分、セキュリティの高さやカスタマイズ性に優れ、独自のニーズに合わせた運用が可能です。
大規模病院や患者数の多い医療機関に適しており、システム障害時にも院内ネットワークのみで安定稼働できるのが強みです。一方で、保守管理やシステム更新は自院負担となるため、長期的な運用コストを含めた計画的な導入が求められます。
月額料金の目安
電子カルテは初期費用だけでなく、月額利用料もかかる点に注意が必要です。クラウド型では月額2〜5万円程度が一般的で、プランによって機能やサポート範囲が異なります。オンプレミス型でも保守サポートやシステム更新料として毎月数万円の維持費が必要となるケースが多いです。
こうしたランニングコストは長期的に大きな負担となるため、初期費用と合わせて総額で比較検討することが大切です。予算を考える際は「導入時の投資」と「運用コスト」の両面を見据えた計画が必要になるでしょう。
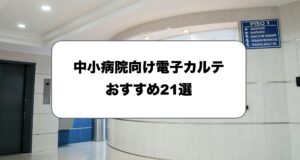
初期費用無料で利用できるサービスもある
初期費用無料で利用できる電子カルテサービスは、特に開業したばかりのクリニックやコストを抑えたい医療機関にとって魅力的な選択肢です。通常、電子カルテの導入にはソフトウェア費用やサーバー設置費、工事費用などで数百万円規模の初期投資が必要となります。
しかし、クラウド型を中心に一部のベンダーでは初期費用を無料とし、月額料金のみで利用できるプランを提供しています。これにより、大きな資金を準備することなく電子カルテを導入でき、事業の立ち上げ段階でもスムーズに利用を開始できます。また、無料トライアル期間を設けているサービスもあり、操作性や機能を事前に確認できる点も安心材料です。
ただし、無料で始められる一方で、月額料金が割高になるケースやオプション追加でコストが膨らむ可能性もあります。そのため、長期的な費用総額を見据えて比較検討することが重要です。
おすすめの電子カルテサービス8選
電子カルテは多くのメーカーが提供しており、機能性や価格帯もさまざまです。ここでは医療機関に導入実績のある代表的なサービスを8つ取り上げ、それぞれの特徴やメリットを解説します。
M3デジカル(エムスリーデジカル)

M3デジカルは、エムスリーグループが提供するクラウド型電子カルテで、操作性の高さと低コストでの導入が強みです。初期費用を抑えつつ、月額課金制で利用できるため、開業医や小規模クリニックに人気があります。
予約管理やレセプト業務に対応しており、オンライン診療システムとの連携も可能です。さらに、M3が持つ医療情報ネットワークとの親和性が高く、診療サポートの面でも活用が期待できます。
Medicomシリーズ(ウィーメックス)

ウィーメックス(旧PHC)のMedicomシリーズは、長年の実績を持つ電子カルテブランドで、信頼性と安定性に定評があります。外来から在宅診療まで幅広く対応でき、レセコンとの高い連携性が強みです。
オンプレミス型とクラウド型の両方を提供しており、医療機関の規模やニーズに合わせて柔軟に導入できます。医療現場の声を反映した継続的な改良により、使いやすさにも配慮されています。
HOPEシリーズ(富士通)

富士通のHOPEシリーズは、大規模病院からクリニックまで幅広い医療機関で導入されている電子カルテです。堅牢なシステム設計とカスタマイズ性の高さが特徴で、複数診療科を持つ病院や地域連携を重視する医療機関に適しています。
データの一元管理により、患者情報を多角的に分析できる点もメリットです。また、サポート体制が整っており、長期的に安心して利用できるシリーズとして評価されています。
BrainBoxシリーズ(株式会社ユヤマ)
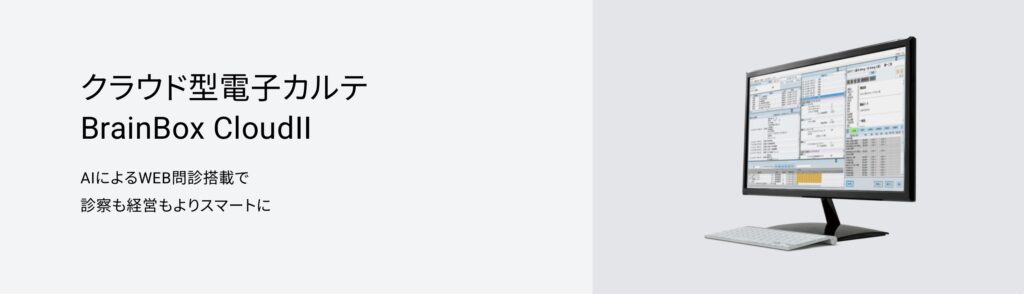
ユヤマのBrainBoxシリーズは、調剤薬局分野で培ったノウハウを活かした電子カルテで、薬歴管理や処方支援に強みがあります。診療所向けに設計されており、操作性がシンプルでスタッフ全員が使いやすい点が特徴です。
患者ごとのデータをスムーズに呼び出せるため、診察効率を高める効果が期待できます。小規模な医療機関でも導入しやすい価格設定も魅力です。
Dynamics(ダイナミクス)

ダイナミクスの電子カルテ「Dynamics」は、クラウド型を中心に提供されており、低コストでの導入とスピーディーな立ち上げが可能です。直感的な操作性に加え、予約・会計・レセプトまで一連の業務をカバーする統合システムが魅力です。
オンライン診療やキャッシュレス決済との連携も進んでおり、最新の医療DXに対応した機能が充実しています。中小規模クリニックを中心に支持を集めています。
Qualisシリーズ(ビー・エム・エル)

ビー・エム・エルが提供するQualisシリーズは、検査会社ならではの強みを持つ電子カルテです。検査結果のスムーズな取り込みや閲覧が可能で、検査依頼から結果確認まで一貫したワークフローを実現します。
外来業務の効率化を重視して設計されており、操作画面もシンプルでわかりやすい仕様です。診療と検査を一体的に管理したい医療機関に最適な選択肢となっています。
SUPER CLINIC(ラボテック)

ラボテックのSUPER CLINICは、操作性とサポート体制に力を入れた電子カルテで、特に開業医や小規模クリニック向けに導入しやすいシステムです。低コストで始められるプランが用意されており、必要最低限の機能から拡張していける柔軟性が特徴です。
予約管理や会計機能との連携により、日常業務を効率化できる点が評価されています。アフターサポートも充実しているため、安心して導入できます。
CLINICS(メドレー)

メドレーが提供するCLINICSは、オンライン診療との連携に特化したクラウド型電子カルテです。スマホやタブレットからも操作できる利便性があり、予約管理や決済機能ともスムーズに連動します。初期費用が抑えられており、導入までのハードルが低いのも魅力です。
オンライン診療を強化したい医療機関にとって、時代に即した選択肢となる電子カルテといえます。
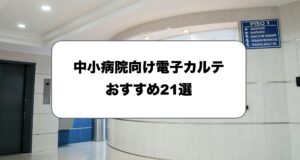
電子カルテの導入費用を抑える方法
電子カルテの導入は数百万円規模の投資になることもありますが、工夫次第で費用を抑えることが可能です。
ここでは、初期費用やランニングコストを軽減するための具体的な方法を紹介します。
クラウド型電子カルテを選び、初期費用を抑える
クラウド型電子カルテはサーバーを院内に設置する必要がなく、初期費用を大幅に削減できる点が魅力です。従来のオンプレミス型では数百万円単位の設備投資が必要でしたが、クラウド型は100〜200万円程度から導入可能で、導入スピードも早いのが特徴です。
さらに、ソフトウェアの更新やセキュリティ管理はベンダー側が担うため、専門知識がなくても最新環境を維持できます。小規模クリニックや新規開業医にとって、資金負担を最小限に抑えながら電子カルテを導入できる現実的な選択肢といえるでしょう。
リースやレンタルを活用して一括購入を避ける
電子カルテ導入時に必要となるPCや周辺機器をリースやレンタルで導入することで、一括購入の負担を軽減できます。特に初期費用が大きくなりがちなオンプレミス型を検討する場合、この方法は有効です。
リース契約なら月額払いにでき、資金繰りを安定させながら最新の機器を利用できます。また、リース期間終了後には機器を入れ替えることも可能で、古い設備を長期間使い続けるリスクも軽減できます。長期的に見てコストは割高になるケースもありますが、初期の資金不足を解消するメリットは大きいといえるでしょう。
無料トライアルや低価格プランを利用してスモールスタートする
多くの電子カルテベンダーでは、無料トライアルや低価格プランを提供しています。これを活用すれば、大きな投資をせずに実際の運用感を確認できます。トライアル期間中に操作性やスタッフの使いやすさをチェックできるため、導入後のギャップを減らすことができます。
また、初めは低価格プランで導入し、必要に応じて機能を拡張していく方法も有効です。特に開業直後のクリニックでは、利用規模が拡大するタイミングに合わせて柔軟にプランを変更できる点が魅力です。スモールスタートを実現することで、無駄な費用を避けつつ安心して導入できます。
複数メーカーの相見積もりを取る
電子カルテはベンダーによって価格設定やサポート内容が大きく異なります。そのため、複数メーカーから相見積もりを取ることは費用を抑える上で欠かせません。見積もり比較を行うことで、不要なオプションが含まれていないかを精査でき、同じ機能でも安価に導入できる可能性が見えてきます。
また、価格交渉の余地が生まれる点もメリットです。システムの使いやすさやサポート体制なども含めて比較することで、単に安いだけでなく総合的に満足度の高い導入が実現します。結果として、費用対効果を最大化する導入が可能になります。
IT導入補助金や自治体の医療機関向け補助金を申請する
電子カルテ導入の大きな助けとなるのが補助金制度です。特に国のIT導入補助金は、電子カルテや関連システムの導入費用に対して最大で数百万円規模の補助を受けられる可能性があります。さらに、自治体によっては医療機関向けに独自の補助金や助成金を設けている場合もあります。
これらを活用することで、初期投資を大幅に軽減でき、導入を後押しする効果が期待できます。ただし、申請には事前準備や採択要件の確認が必要なため、早めに専門家やベンダーに相談して進めることが重要です。補助金を上手に活用することが、費用削減の大きな鍵となるでしょう。
電子カルテ導入に利用できる補助金・助成金
電子カルテの導入には数百万円規模の費用が発生することもありますが、補助金や助成金を活用することでコストを大幅に削減できます。
ここでは代表的な制度として「IT導入補助金」と「業務改善助成金」を紹介します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者のIT化を支援する制度で、電子カルテも対象に含まれます。補助率は最大2分の1から3分の2程度で、ソフトウェアの導入費用やクラウド利用料の一部が支援されます。
たとえば100万円の導入費用がかかる場合でも、補助を受けることで実質負担を半額以下に抑えられるケースがあります。申請には、登録されたITベンダーを通じた計画策定が必要で、採択後も成果報告や事業実施状況の提出が求められます。医療機関にとっては、限られた予算の中で電子カルテを導入する強力な後押しとなる制度です。
業務改善助成金
業務改善助成金は、厚生労働省が実施する制度で、生産性向上を目的とした設備投資やシステム導入を支援します。電子カルテの導入によって業務効率が高まり、従業員の労働環境改善や人件費削減につながる場合、この助成金を申請することが可能です。
助成額は最大で数百万円に及ぶ場合もあり、特に人手不足や働き方改革を進めたい医療機関にとって有効です。申請には就業規則の整備や最低賃金引き上げといった条件が付与されるため、事前の準備が欠かせません。条件を満たせば電子カルテ導入費用の一部をカバーできるため、導入のハードルを下げる有力な支援策となります。
電子カルテの導入費用に影響する要因は?
電子カルテの導入費用は一律ではなく、システムの種類や医療機関の規模、求める機能によって大きく変動します。
ここでは、導入費用に影響する代表的な要因を解説します。
導入する電子カルテがクラウド型かオンプレミス型かの違い
電子カルテの導入形態は費用に直結します。クラウド型はサーバー設置が不要なため初期費用を100〜200万円程度に抑えられる一方、毎月の利用料が発生します。
オンプレミス型は自院にサーバーを構築する必要があり、初期費用が250〜400万円以上になるケースも珍しくありません。その分カスタマイズ性やセキュリティ性に優れ、大規模病院では導入メリットが大きいといえます。
医療機関の規模(クリニック・中規模病院・大規模病院)
医療機関の規模によって必要な端末数や機能が変わり、導入費用も大きく異なります。小規模クリニックでは最低限の機能で十分な場合が多く、費用も比較的抑えやすいです。中規模病院になると複数診療科や部門間でのデータ連携が必要となり、機能拡張や端末追加によってコストが増加します。
大規模病院ではさらに高度なカスタマイズやセキュリティ対策が求められ、費用は数千万円規模に達することもあります。
必要とする機能やオプションの有無
電子カルテの基本機能に加えて、予約管理、レセプト請求、オンライン診療対応、在宅医療支援などのオプションを追加すると費用が上がります。特に、外部システムとの連携やカスタマイズ性の高い機能は開発費や設定費が加算され、全体の導入費用に大きな影響を与えます。
必要な機能と不要な機能を見極めることが、無駄なコストを避けるためのポイントになります。
ハードウェア(PC・サーバー・周辺機器)や工事費用
電子カルテの運用には、PCやタブレット、プリンター、サーバーなどの機器が不可欠です。さらに、ネットワーク環境の整備や配線工事などの初期インフラ費用も発生します。
クラウド型の場合は比較的少額で済みますが、オンプレミス型では高性能サーバーや専用機器が必要となり、数百万円単位の費用が追加されるケースもあります。
保守サポートや教育研修など運用体制にかかるコスト
導入後も継続的に発生するのが保守サポートやスタッフ教育の費用です。システムの安定稼働やセキュリティ維持には、定期的なアップデートや障害対応が欠かせません。
また、医師や看護師、事務スタッフがシステムを使いこなすための研修にもコストが必要です。特に大規模病院では研修対象者が多いため、その分の費用負担も大きくなります。運用体制にかかるコストは、長期的に導入費用全体を左右する重要な要因です。
電子カルテを探すなら一括資料請求サービスへ!
これから電子カルテ導入をお考えの方は、無料の一括資料請求サービスをご利用ください。
サービス比較.comでは、複数会社への一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
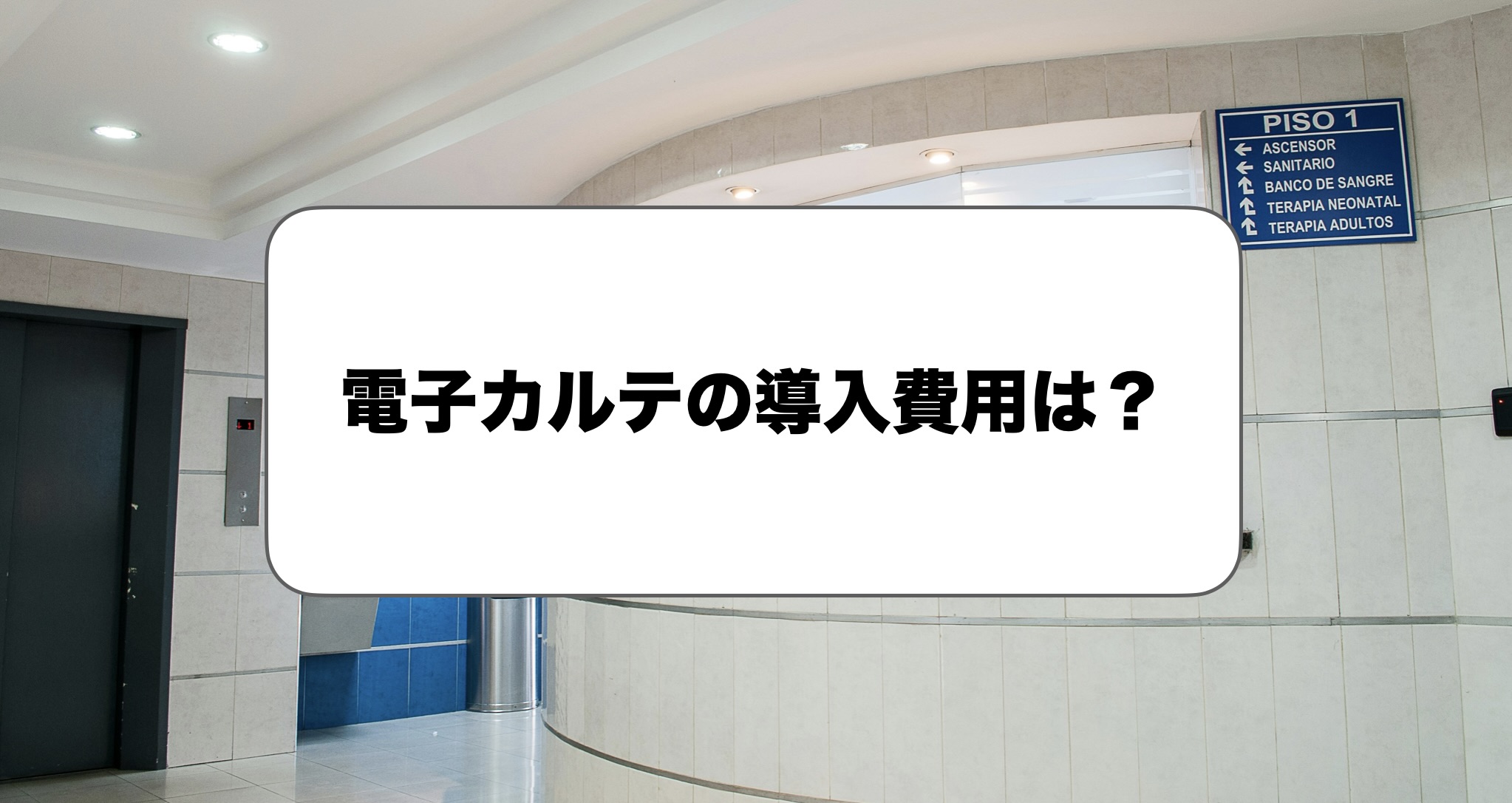

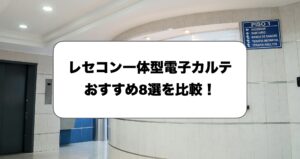
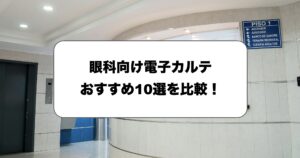
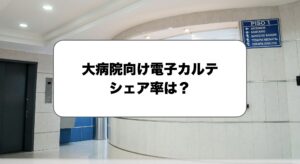
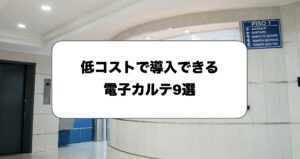
コメント