領収書の発行の基本ルールがわからない
領収書の発行を効率化したい
このようにお悩みではないでしょうか。
これからPOSレジの導入をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

導入相談実績1000件以上!
セルフレジ・POSレジのことならお任せください。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
領収書の役割とは?

ここからは、領収書の役割について解説します。
商品を購入した証明になる
領収書は、購入者が商品やサービスの代金を支払った事実を公式に証明する書類です。日付、金額、取引内容、発行者の情報が明記されており、支払いが正しく行われたことを第三者にも示せます。消費者にとっては、商品が不良品だった場合の返品や交換の根拠として活用でき、また保証期間の確認にも役立ちます。
ビジネスにおいては、取引先との支払い確認や契約履行の証拠としても利用されます。特に高額商品や長期保証の製品では、領収書がないとサービスを受けられない場合もあるため、発行後は必ず保管しておくことが重要です。
経費処理に使用する
法人や個人事業主にとって、領収書は経費計上に不可欠な証拠書類です。会議費、交通費、備品購入費など、事業活動に必要な支出を経費として処理する際、領収書があることで税務上の根拠が明確になります。
領収書には支払日、支払先、金額、内容が記載されており、これを会計ソフトや帳簿に記録することで正確な経理処理が可能になります。税務調査の際には、経費の正当性を証明する重要な資料となるため、領収書を紛失すると経費が認められない可能性があります。したがって、日々の取引で受け取った領収書は速やかに整理・保管することが求められます。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
領収書発行が可能なおすすめのPOSレジ3選
ここからは、領収書発行が可能なPOSレジについて解説します。
スマレジ【おすすめNo.1】

スマレジは、操作性と機能性のバランスに優れたクラウド型POSレジで、飲食店や小売店を中心に幅広く導入されています。価格はスタンダードプランが無料で利用でき、必要な機能に応じてプレミアム(月額5,500円)やプレミアムプラス(月額8,800円)へのアップグレードも可能です。売上分析や在庫管理、会員管理など店舗運営を支える機能が充実しており、複数店舗展開にも柔軟に対応します。
また、スマホやタブレット端末を利用できるため、初期投資を抑えつつ高機能なレジ環境を構築できます。周辺機器やキャッシュレス決済端末との連携もスムーズで、業務効率化や顧客満足度の向上に直結する点が大きな魅力です。
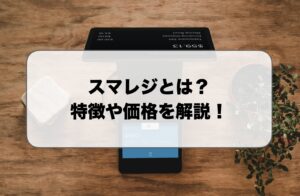
CASHIER POS

CASHIER POSは、業種や店舗規模を問わず導入しやすいシンプル設計のクラウドPOSレジです。スタータープランは無料で利用でき、基本的なレジ機能に加えて、売上データの自動集計やクラウド上でのデータ管理が可能です。プロフェッショナルプラン(月額4,400円)では高度な分析機能や在庫管理、顧客管理が追加され、モバイルオーダープラン(月額3,000円)ではスマホからの事前注文・決済にも対応します。
導入は短期間で行えるうえ、既存の端末を活用できるため初期費用も抑えられます。軽快な操作性とシンプルなUIにより、スタッフ教育が容易で、複数店舗の売上管理にも適しています。
POS+ selfregi【サポートが手厚い】

POS+ selfregiは、セルフレジ機能とPOS管理を一体化させたシステムで、省人化と業務効率化を同時に実現できます。月額14,000円から利用でき、飲食店・小売店・サービス業など幅広い業種に対応しています。最大の特徴は、導入時から運用後まで手厚いサポート体制が整っている点です。
初期設定や操作説明、トラブル対応などを専門スタッフがサポートし、ITが苦手な店舗でも安心して運用できます。また、セルフレジ化により会計待ち時間の短縮や人件費削減が可能で、顧客満足度の向上にもつながります。売上や在庫のリアルタイム管理も可能で、多店舗展開やピークタイムの混雑解消に効果的です。
失敗しないPOSレジの選び方
POSレジを導入する際は、機能・操作性・連携・サポートなど複数の観点から慎重に選ぶことが大切です。店舗運営にフィットしたPOSレジを選べるよう、押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
導入目的を明確にし、必要な機能や課題を整理する
POSレジ選びで最初に取り組むべきなのは、導入目的を明確にすることです。会計スピードの向上、売上管理の効率化、人件費削減、ミス防止など、抱えている課題によって選ぶべきPOSの種類や機能は大きく変わります。
飲食店なら注文管理・キッチン連携、テーブル会計、小売店なら在庫管理やバーコード運用など、業種に合った機能の有無が重要です。また、キャッシュレス決済の比率や将来の店舗拡大予定なども整理しておくと、長期的に使いやすいPOSレジを選択できます。
目的を先に固めておくことで、複数の製品を比較する際の判断軸が明確になり、導入後のトラブルや「思っていた機能がなかった」という失敗を防ぐことにつながるでしょう。
使いやすい操作画面で、スタッフが迷わず扱えるかチェックする
POSレジを選ぶ際は、現場で実際に使用するスタッフが直感的に操作できるかを重視する必要があります。どれだけ高機能でも、操作が複雑だと会計の遅延やミスにつながり、店舗の生産性を下げてしまいます。
特に飲食店のピークタイムや小売店の繁忙期では、操作のわずかな迷いが行列や接客の停滞を引き起こすでしょう。そのため、ボタン配置のわかりやすさ、レイアウトの見やすさ、操作ステップの少なさなど、誰でも使いやすいUI設計がされているかをチェックすることが大切です。
実機デモを確認し、アルバイトスタッフや新人でもすぐ使えるかどうか、実際の業務フローに沿って試すことで、導入後の現場負担を大幅に減らせます。
周辺機器や決済端末との連携性が高いか確認する
POSレジは単体で動くものではなく、釣銭機・バーコードリーダー・プリンター・決済端末などとの連携が重要です。連携性が弱いと、機器ごとに操作が必要になったりデータが同期されなかったりと、業務効率が低下してしまいます。
特に飲食店では、券売機やキッチンプリンターとの連携、小売店では在庫管理システムやECとの同期など、日々の運用で必要な機能が多く存在します。また、キャッシュレス決済が増える中で、クレジット・QR・電子マネーなど多様な決済手段に対応できるかも非常に重要です。
導入予定の周辺機器との相性や、将来的な追加機器への拡張性も確認し、店舗運営に合った連携環境を整えられるPOSレジを選ぶことが失敗しないポイントとなります。
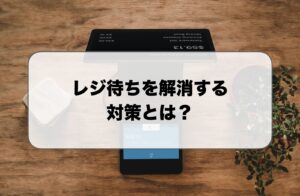
サポート体制や保守内容が十分かどうか確認する
POSレジはトラブルなく使い続けるために、導入後のサポートと保守体制の充実度が非常に重要です。万が一システム不具合が起きると、会計が止まり、売上にも直結する大きな問題になります。
そのため、サポートの受付時間、チャット・電話対応の有無、遠隔サポートや駆けつけ対応のスピードなどを必ずチェックしましょう。特に飲食店のピークタイムにトラブルが起きると大きな損失になるため、迅速な復旧が可能な手厚いサポートを選ぶことが安心につながります。
また、ソフトウェアのアップデート頻度、POS周辺機器の故障時対応、交換費用なども事前に確認しておくと、予期せぬコストや運用トラブルを防げます。費用の安さだけで選ぶのではなく、長く安定して使えるサポート品質を重視することが成功の鍵です。
領収書の保存義務について
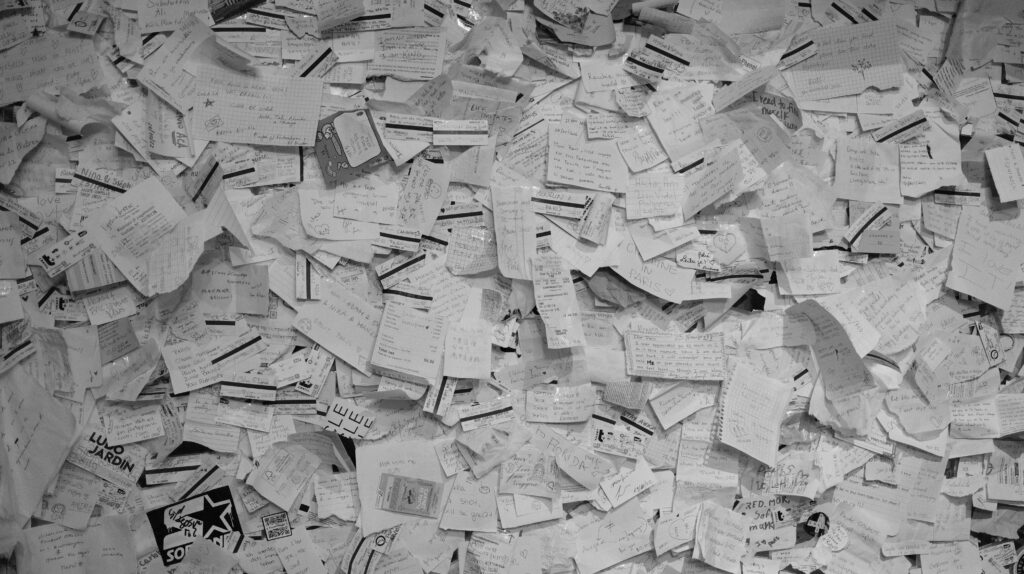
税法上、法人や個人事業主は領収書を一定期間保存する義務があります。原則として、法人税法や所得税法では帳簿書類とともに領収書は7年間、消費税法では課税仕入れに関する書類を7年間保存することが求められます(ただし、青色申告の欠損金がある場合は最長10年間)。これは税務調査や監査の際に、取引の正当性や経費計上の根拠を示すためです。
保存方法は紙のままでも、スキャナ保存制度を利用して電子データとして保管することも可能です。ただし、電子保存の場合は改ざん防止や検索性の確保といった要件を満たす必要があります。保存期間を過ぎるまでは廃棄せず、適切に管理することが重要です。
領収書と領収証・レシートの違い
領収書・領収証・レシートはすべて支払いを証明する書類ですが、用途や形式に違いがあります。一般的に「領収書」と「領収証」は同じ意味で使われ、取引内容や金額、発行者情報などが記載された正式な証明書です。ビジネスや税務処理に用いることが多く、宛名や但し書きの記載も重要です。
一方、レシートはPOSレジから自動印字される簡易的な証明書で、購入商品名や数量、単価が詳細に記載されます。レシートも法的には領収書として認められますが、宛名や但し書きが不要な場合が多いため、正式な請求・経費証明が必要な場面では領収書・領収証の発行が望まれます。
領収書に印字すべき記載内容

領収書は単なる支払い証明ではなく、税務処理や経費精算において重要な法的証拠となる書類です。
以下では、領収書に必ず印字すべき項目とその役割を解説します。
発行日(領収書を発行した日付)
領収書の発行日は、実際に金銭のやり取りが行われた日を正確に記載します。これは税務処理や経費計上の期間判定に直結し、誤った日付は経理上の不整合を招く可能性があります。後日発行する場合でも、支払日を基準とするのが原則です。
特に年度末や月末の取引では日付のずれによって計上年度が変わるため、正確さが重要です。また、発行日を明確にすることで、保証期間や返品期限の判断にも役立ちます。
宛名(顧客名、または「上様」など)
宛名は領収書の受取人を明確にするために記載します。法人の場合は正式な会社名を、個人の場合は氏名を正しく記載します。「上様」とすることも可能ですが、税務調査では具体的な宛名の方が経費計上の信頼性が高まります。
誤った宛名や空欄は証憑としての効力が弱まり、経費が認められないリスクがあります。特に取引先や顧客に提出する場合は、正式名称を確認してから記載することが望まれます。
金額(消費税を含んだ税込金額)
領収書には支払金額を税込みで記載します。消費税額を明確にするために「本体価格」と「消費税額」を分けて記載するケースもあります。金額は数字の前に「¥」や「金」を付け、改ざん防止のために数字の後に「-」や「也」を付けることもあります。
金額の記載ミスは重大なトラブルの原因となるため、発行前に必ず確認が必要です。
但し書き(取引内容の簡単な説明。例:「飲食代として」など)
但し書きは、領収書の支払い目的を簡潔に記載する欄です。例として「飲食代として」「備品代として」などがあり、税務上はこの記載があることで経費性を証明しやすくなります。
あまりに抽象的な表現(例:「品代」)は税務調査で指摘される可能性があるため、可能な限り具体的に記載することが望ましいです。
発行者の氏名または会社名・店舗名
領収書には、発行者の正式な氏名または会社名・店舗名を記載します。法人の場合は登記上の正式名称、個人事業主の場合は屋号や本名を用います。発行者の特定ができないと証拠能力が低下し、税務上の問題となることがあります。
発行者の住所および連絡先
発行者の所在地や連絡先は、取引先や税務署が発行者を確認するために必要です。住所は都道府県から正確に記載し、電話番号やメールアドレスを併記することもあります。特に会社間取引では所在地の記載は必須です。
押印または署名(企業名だけでも可だが、実務上は印鑑が望ましいケースも)
発行者欄には押印や署名を行うことで、領収書の信頼性を高めます。法人では角印や社判を押すのが一般的で、改ざん防止にもなります。署名だけでも法的効力はありますが、商習慣上は印鑑を用いる方が望ましいです。
収入印紙の貼付欄(5万円以上の現金取引の場合は必要)
収入印紙は、印紙税法で定められた金額以上の取引に必要です。現金取引で5万円以上の場合は印紙を貼付し、割印を行います。クレジットカードや振込の場合は不要ですが、現金の場合は貼り忘れに注意が必要です。貼付漏れは発行者側の罰則対象になるため、経理担当は必ず確認します。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
POSレジで領収書を発行する方法

POSレジでは、会計処理と同時に領収書を発行できるため、手書きよりも迅速かつ正確に対応できます。発行の流れは店舗やPOSレジの機種によって多少異なりますが、基本的な手順は以下の通りです。
1.通常どおり会計処理を行う
まず、POSレジで商品のスキャンや金額入力を行い、通常の会計手続きを進めます。会計方法(現金・クレジット・QR決済など)を選択し、支払いが完了した時点で領収書発行が可能になります。この時点で取引内容や金額はPOSレジに正確に記録されているため、領収書作成時の記載ミスが防げます。
2. 「領収書印刷」を選択する
会計完了後、POSレジ画面の「領収書発行」または「領収書印刷」ボタンをタップします。機種によっては会計時に同時発行できる設定や、後から発行する機能もあります。顧客からの要望があった場合は、この時点で発行手順に進みます。
3. 宛名を入力する(例:「青空 太郎 様」)
領収書には宛名の記載が必要です。POSレジの入力欄に顧客の氏名や会社名を正確に入力します。「上様」とすることも可能ですが、経費処理上は具体的な宛名の方が望ましいです。誤入力を防ぐため、顧客に口頭で確認するのが安心です。
4. 但し書きを選択する(例:「ご飲食代」「お品物代」など)
取引内容を簡潔に示す但し書きを入力または選択します。POSレジにはあらかじめ複数の但し書きが登録されている場合が多く、用途に応じて選択できます。税務上は具体性がある記載が好ましいため、「品代」よりも「飲食代」や「備品購入代」などを選ぶのが望ましいです。
5. 印刷する
宛名・但し書き・金額を確認後、領収書を印刷します。POSレジ連動のレシートプリンターから正式な領収書が出力されます。印刷前に内容確認を行い、誤字や金額のミスがあれば修正します。
6. 必要に応じて収入印紙を貼付し、割印を行う
現金で5万円以上の取引の場合は、印紙税法に基づき収入印紙を領収書に貼付し、割印を行います。クレジットカードや振込での決済では印紙は不要ですが、現金取引では必須です。貼付漏れは罰則対象になるため注意が必要です。
7. お客さまに領収書を渡す
印刷した領収書を確認し、必要に応じて印鑑を押してからお客さまへ手渡します。取引終了後に「ご利用ありがとうございました」と一言添えることで、接客印象も良くなります。発行済み領収書はPOSレジにもデータとして記録され、再発行や売上管理にも活用できます。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
POSレジで領収書を発行するときのポイント

以下では、POSレジで領収書を発行する際に押さえるべき8つのポイントを解説します。
領収書とレシートを併せて渡さない(二重発行を防ぐ)
領収書とレシートはどちらも支払い証明としての効力がありますが、両方を同時に渡すと同一取引の二重発行とみなされ、不正利用や経費の二重計上の恐れがあります。顧客から両方求められた場合は、いずれか一方を渡し、もう一方は回収するか「領収書発行済」などと記載して渡すのが安全です。
宛名や但し書きは必ず記載し、空欄にしない(不正利用のリスクを防ぐ)
宛名や但し書きが空欄だと、領収書を第三者に転用される恐れがあります。特に但し書きは「飲食代」「備品代」など具体的に記載し、取引の内容を明確にします。空欄のまま渡すのは不正利用や税務否認のリスクが高く、避けるべきです。
宛名は略さず正式名称で記載する(例:「株式会社」まで明記)
宛名を略すと、正式な経費証明としての効力が弱まる場合があります。法人名の場合は「㈱」ではなく「株式会社」と正式表記し、個人名もフルネームで記載します。特に税務調査時には、正式名称が記載されている方が信頼性が高く評価されます。
税抜5万円以上の現金取引には収入印紙を貼り、割印を行う
印紙税法では、現金で5万円以上の取引に対して領収書を発行する場合、収入印紙を貼付し割印を行う必要があります。貼り忘れは発行者が過怠税を負担することになるため、現金取引時は必ず金額を確認し、印紙の有無を判断します。
クレジットカード決済の場合は収入印紙は不要(カード利用の旨を明記する)
クレジットカードやQRコード決済は印紙税の対象外です。ただし、領収書に「クレジットカード利用」や「〇〇Pay利用」などと記載し、現金取引でないことを明確にします。これにより印紙税の誤適用を防げます。
押印は必須ではないが、信頼性やビジネスマナーとして押すのが望ましい
法律上は押印がなくても領収書としての効力はありますが、商習慣上は発行者印を押す方が望ましいです。特に法人間取引では、角印や社判を押すことで信頼性が高まり、顧客からの安心感にもつながります。
発行した領収書の控えは帳簿書類として7年間(青色)、5年間(白色)保存する
法人税法・所得税法では、発行した領収書の控えを一定期間保存する義務があります。青色申告の場合は7年間、白色申告は5年間が保存期間です。紙だけでなく、スキャナ保存制度を利用して電子データで管理することも可能です。
記載内容に不備があった場合は正しい内容で再発行する
誤記や記載漏れがあった場合は、訂正印で修正するよりも新しく正しい領収書を再発行する方が望ましいです。再発行時には、旧領収書を回収または「作成ミスにつき無効」と明記して保管し、二重発行や誤用を防ぎます。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
POSレジで領収書を発行するメリット
ここでは、POSレジで領収書を発行するメリットについて解説します。POSレジを活用することで、手書き発行よりも発行スピードや正確性が向上し、業務効率化が実現できます。
手書きよりも早く、スムーズに発行でき業務効率が向上する
POSレジは会計と同時に領収書を印刷できるため、手書き作業に比べて発行時間を大幅に短縮できます。特に飲食店や小売店のピークタイムでは、お客様を待たせずに素早く対応できる点が大きな利点です。
手書きの場合は金額や宛名、日付の記入に時間がかかりますが、POSレジでは会計データが自動反映されるため、数秒で発行可能です。これにより、スタッフの負担軽減と回転率の向上が実現します。また、オペレーションが簡素化されることで新人スタッフでもすぐに対応でき、教育コストの削減にもつながります。
金額や日付などの入力ミスが減り、正確な発行ができる
POSレジでは会計時に入力された金額や日付がそのまま領収書に反映されるため、手書きで発生しやすい記入ミスを大幅に減らせます。日付や金額の誤りは税務処理や顧客対応で大きなトラブルに発展する可能性がありますが、POSレジの自動入力機能によりそのリスクを最小化できます。
さらに、税率や消費税額も自動計算され、税込・税抜表示も正確に行われます。こうした正確性は、税務調査や経費精算の際にも信頼性の高い証憑として機能し、店舗運営の透明性向上にも寄与します。
宛名・但し書きなどの定型文を簡単に選べるため対応が標準化できる
POSレジにはあらかじめ宛名や但し書きのテンプレートを登録しておくことができ、発行時にはそれらを選択するだけで入力が完了します。これにより、スタッフごとの表記ゆれや記載漏れを防止し、統一されたフォーマットで領収書を発行できます。
特に複数店舗を運営する場合やスタッフ数が多い店舗では、記載内容の統一は企業ブランドの信頼性向上にも直結します。また、頻繁に使用する但し書きや宛名を登録しておけば、入力時間も短縮でき、顧客対応のスピードアップと業務効率化が同時に実現します。
売上や発行履歴がPOS内に記録され、管理や再発行がしやすい
POSレジは領収書の発行履歴を自動的に保存するため、過去の発行記録を簡単に検索・確認できます。万が一、顧客から再発行の依頼があった場合も、該当データを呼び出して素早く再発行が可能です。紙の控えを探す必要がなく、管理コストも削減できます。
さらに、発行履歴は売上データと紐づいて保存されるため、経理や税務処理の際にも便利です。こうした記録の一元管理は、店舗の信頼性向上やコンプライアンス強化にもつながります。
電子領収書にも対応し、ペーパーレス運用が可能になる
多くのPOSレジは電子領収書の発行機能を備えており、メールやQRコードを通じて顧客へデータ送付が可能です。これにより紙の使用量を削減でき、環境負荷低減や印刷コスト削減が期待できます。顧客にとっても紛失のリスクが減り、データとして保管できる利便性があります。
さらに、電子領収書は会計システムとの連携もしやすく、経理業務の効率化に貢献します。今後のキャッシュレス化やDX推進の流れにも対応できる点が大きな魅力です。
領収書発行後に会計ソフトや顧客データと連携しやすい
POSレジで発行した領収書データは、そのまま会計ソフトや顧客管理システムと連動させることができます。これにより、売上や経費データの入力作業が自動化され、経理業務の効率化が実現します。
また、顧客情報と紐づけることで、購買履歴や来店傾向の分析が可能になり、マーケティング施策にも活用できます。データの一元管理により、販売から経理・営業までの業務がシームレスにつながり、店舗運営全体の生産性向上に寄与します。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
POSレジの導入ならレジコンシェルジュへ!
これからPOSレジの導入をお考えの方は、レジコンシェルジュへご相談ください。
レジコンシェルジュでは、複数メーカーへの一括資料請求やお見積もりなどについて完全無料で行っております。
どの製品を選べば良いか分からない方も、以下のリンクよりご相談いただければすぐさまぴったりのサービスが見つかります。
まずはお気軽にご相談ください。
POSレジの専門知識を持ったコンシェルジュが、ご要望に合わせて最適なサービスを紹介させていただきます。
専門知識が無くても、手間を掛けずに最短でPOSレジを見つけることが出来ます。
非公開となっている情報や相場などもご相談いただけますので、まずはお気軽お問い合わせください。
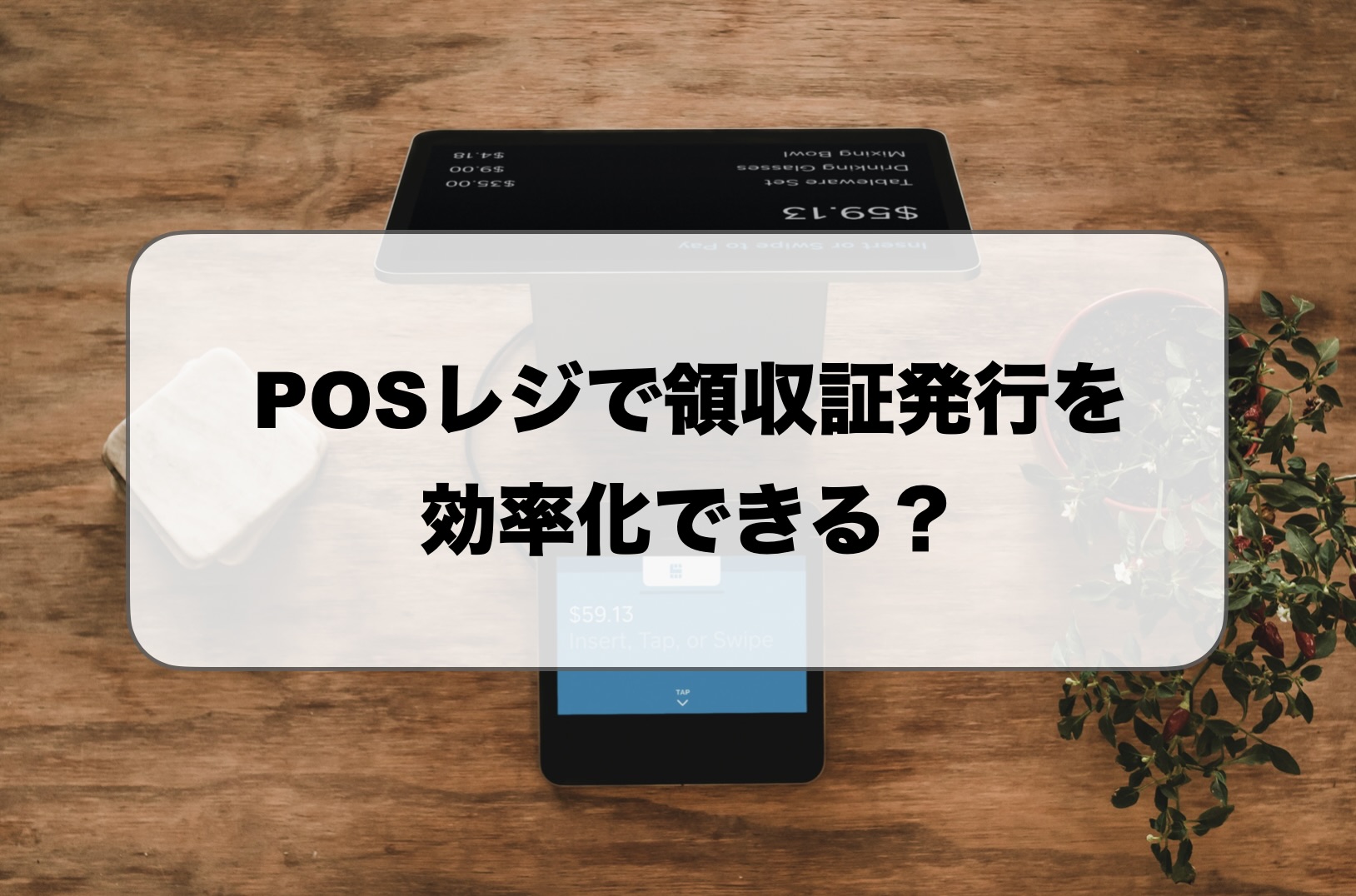







コメント